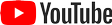鞄を選ぶとき底鋲まで気にする人はいないと思いますが

鞄に特有のパーツで底鋲というものがあります。鞄の底革が直接地面に触れないようにする金属製の鋲で、稀に革で作ることもあります。小さいトートや柔らかい袋ものにはありませんが、大きくしっかりした鞄には大抵備わっています。底鋲まで気にして鞄を選ぶことはないと思いますが、作る側は底鋲を選んでいるという話です。
底鋲の色々

普段はあまり見えないので形や色を気にしない方も多いと思います。色々ありますが自分は真鍮無垢の物が好きでそればっかり使ってます。真鍮製無垢以外にもニッケルメッキや金、ブロンズなどにメッキされたものがありますし、樹脂製やゴム製もあるようです。
鉄にメッキされたものは、はがれた時にかっこ悪いので地金の方が良いかと思っています。底鋲を底革に固定する方法も1つではありません。
ビスで止めるもの、ツメを折り返して固定するもの、カシメのように打ち込むものなどあります。
ツメは耐久性に不安があるので使いません。高い鞄を買って爪が開いて底鋲が取れたら嫌ですよね。大きな鞄にはそれなりに重さが加わると考えた方が良いです。
カシメは一見丈夫そうですが負荷がかかると緩むと考えられます。打ち込むことで変形する金属の固定力に依存しています。それなりに柔らかい金属ということができます。
秀革堂ではより耐久性のあるビス止めを使っています。ビス止めの良いところはしっかり固定できるところ。底の厚さに合わせてビスの長さを調整できることです。グラインダー等で加工すればそれぞれの鞄に合った最適な長さのビスを用意できます。それをネジロック剤を使って固定します。
ツメ折り式やカシメ式は金属板を加工して作られているので底鋲本体の内側は空洞になっています。一方、ビス止め式の底鋲は鋳物のかたまりを使っているので底鋲自体の耐久性も高いと考えられます。
その分重いのが難点ではありますが・・。底鋲だけを手に乗せてもずっしりとその重さを感じます。ただでさえ重さの点で不利と言われる革鞄ですが、そのデメリットがあっても使いたいのがビス止め式の底鋲なのです。
真鍮製

そんなビス止め式底鋲の多くは真鍮製です。
真鍮は銅と亜鉛の合金で黄銅などと呼ばれ、五円玉にも使われていますね。英語では「brass」。ブラスバンドの管楽器も真鍮ですね。
真鍮の魅力は磨きたては鮮やかな黄金色ですが時間と共にくすんでアンティークのような経年変化を見せることにあります。素朴でクラシカルな雰囲気になると感じています。そのためエイジングを楽しむヌメ革と相性がいいのです。
一方でエイジングしないクロムなめしの鮮やかな革にはピカピカのクロムメッキが似合うことが多いです。それでも秀革堂では真鍮製を使う事が多いです。やはり長く使うことを考えるとメッキのはがれが気になるので。しかし近年、真鍮鋳物のメッキではがれにくいとされている物もあるので今後試していこうと思っています。
底鋲の高さ(厚み)



底鋲の高さをある程度確保していないと革が地面に擦れてしまいます。鞄に底板が無い場合はもちろんですが、底板があっても重い荷物で沈んでしまい革が擦れる事は良くあります。
また、柔らかい革で作った鞄の場合、底板があっても胴版の下部が擦れてしまったりします。この場合設計ミスと考えるか許容範囲と考えるかは持ち主次第です。
秀革堂でよく使うのは高さ6〜10mmの底鋲です。ベルポーレンと呼ばれる帽子のつばなどに使われる樹脂製の板を底板にして5、6個使うのが定番です。
定番底鋲
普段あまり目につかない部分ですが気にしだすと気になります。いろいろな鞄の底鋲を見て自分のお気に入りを探してみてください。
当店でよく使う底鋲の画像です。



メッキされたものはゴールド、クロム、ガンメタの3種類。真鍮鋳物にメッキしてあります。やはりずっしり重い底鋲は安心感あります。
ちょっとマニアックな底鋲の話でした。